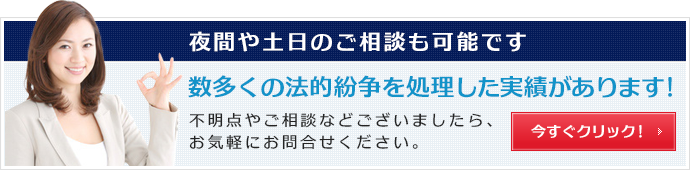原告は、指定商品「キーホルダー、おもちゃ」等について、「melonkuma(標準文字)の商標権を有しています。被告は、大きく開いた口にメロン色の肌、短い手足を特徴とする北海道夕張市のご当地キャラクターを創作し、このキャラクターのキャラクターグッズに「メロン熊ストラップ」、「メロン熊マグネット」、「メロン熊ボクサーパンツ」等の標章を付して販売していました。原告は、被告の各標章の使用は、原告の商標権を侵害するものであるとして、損害賠償請求をしました。
大阪地裁は、「被告各標章は、いずれも『メロン熊』又は『メロンくま』に商品の種類に関する記述を続けるものであり、その要部は『メロン熊』又は『メロンくま』であるといえる。...原告商標は、9文字のローマ字からなる外観を有するのに対し、被告各標章の『メロン熊』の部分は、片仮名3文字と漢字1文字の合計4文字よりなる外観を、被告各標章の『メロンくま』の部分は、片仮名3文字と平仮名2文字の合計5文字よりなる外観を有し、両者は外観において類似しない。原告商標も被告各標章も称呼は同じ『メロンクマ』である。観念について検討するに、原告商標は、ローマ字(小文字)で『melonkuma』と一連一体に表記されるため、この表記に接した者は、そのような外国語の単語があるのではないかと考えるが、これに適応する単語がないため、直ちには特定の観念を生じない。もっとも、そのまま発音することにより、果物のメロンと動物の熊という2つの観念が想起される。しかし、本件キャラクターが出現するまでに、被告以外の第三者が、果物のメロンと動物の熊を組み合わせた存在を、具体的なイメージとして考案したと認めるに足りる証拠はなく、原告商標のみからは、メロンと熊を結合させた、ひとつのものとしての観念を想起させることはないといえる。被告各標章のうち『メロン熊』又は『メロンくま』については、『メロン』と『熊』(『くま』)が片仮名と漢字(平仮名)で書き分けられているため、直ちに果物のメロンと動物の熊という2つの観念を想起することができ、さらに、前記1(1)から、メロンの中に顔を突っ込んだ、メロンと熊がひとつに結合された本件キャラクターを観念することができる。以上によると、原告商標と被告各標章のうち『メロン熊』又は『メロンくま』の部分は、称呼においてのみ類似している。...被告商品のうち、少なくとも、マグネット、ビックマスコット、ぬいぐるみマスコットは、原告商標の指定商品であるおもちゃ、人形と同一、あるいはこれに類似するといえる。...本件キャラクターは、被告代表者が考案したものであって、北海道夕張市を代表するものとして、遅くとも平成22年末頃には、そのキャラクター誕生にまつわるエピソードも含め、全国的に周知性、著名性を獲得したものと認められ、かつ、そのキャラクターが人気を博したことから、強い顧客吸引力を得たものと認められる。そして、その周知性、著名性や顧客吸引力は、被告代表者の努力により、現在においても維持発展されていることも認められる。これに伴い、片仮名の『メロン』と漢字の『熊』(平仮名の『くま』)を組み合わせてなる『メロン熊』(『メロンくま』)との標章(語句)も、本件キャラクターを指し示すものとして周知性、著名性を獲得し、したがって、本件キャラクター及びゴチック体調の『メロン熊』の標章(被告各標章に共通する部分となる標章)は、被告の扱う商品について高い自他識別能力を獲得したものというべきである。...また、...被告各標章が、本件キャラクターとともに使用され、かつ、北海道夕張市に由来することを示す各種語句とともに使用されており、他人の商品役務との誤認混同が生じることのないような措置がされていると評価できる。...他方、原告商標の出願は、平成19年6月にされてはいるが、その後、原告商標の商標権者及び通常実施権者はもちろん、被告以外の第三者が、上記標章の著名性の獲得に至るまでに、果物のメロンと動物の熊を組み合わせた存在を、具体的なイメージとして考案したと認めるに足りる証拠はなく、また、現在までに、被告以外にそのような存在を使用した商品が流通したことを認めるに足りる証拠もない。実際、原告商標については、特許庁において、不使用を理由とする取消審判がされている。...もともと被告各標章には特段の自他識別能力がある一方、原告商標は、登録後、少なくとも、流通におかれた商品に使用されてはおらず、原告商標自体、原告の信用を化体するものでもなく、何らの顧客誘因力も有しているともいえない。そして、原告商標と被告各標章との間で出所を誤認混同するおそれは極めて低い。それにもかかわらず、原告は、原告商標権に基づき損害賠償請求をするものであるが、このような行為は、本件キャラクターが周知性、著名性を獲得し、強い顧客吸引力を得たことを奇貨として、本件の権利行使をするものというべきである。また、前記1で認定した原告商標の登録取消審決に至る経過をみると、本件訴訟の提起自体が、上記審判に対する対抗手段として行われた疑いが強いというべきである。以上によると、原告商標と被告各標章が誤認混同のおそれがあるとしても、原告による権利行使は、商標法上の権利を濫用するものとして、許されないというべきである。」として原告の請求を棄却しました。
melonkuma事件 大阪地裁平成26年8月28日判決
法律のことならお任せ。商標や不正競争防止法のことなら虎ノ門法律特許事務所へ。