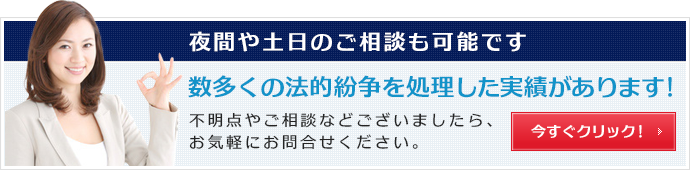原告は、アイスやお菓子の製造メーカーである井村屋グループ株式会社です。原告は商標「あずきバー」という標準文字からなる商標(以下、「本願商標」とします。)について、第30類の「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」を指定商品として平成22年7月5日に出願しました。原告は本願商標について平成23年4月5日付けで拒絶査定を受けたので、同年8月5日これに対する不服の審判を請求しました。特許庁は、これを不服2011-16950号事件として審理し、平成24年6月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は、同年7月11日、原告に送達され、原告はこれを不服として本件訴訟を提起しました。
本件の争点は3つです。
争点1:商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤り
争点2:商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤り
争点3:商標法4条1項16号該当性に係る認定判断の誤り
知財高裁は以下のように判断しました。
争点1:商標法3条1項3号該当性に係る認定判断の誤りについて
知財高裁は、「『あずき』という語を食物の名称の冒頭に付して複合語とした場合、当該複合語は、一般に、小豆又はそれから作られた成分を含有する食品を意味するものと理解される。また、『バー』という語は、(省略)菓子類に関する辞典には、『原義は棒、棒状のもの。【1】棒状の菓子や氷菓のスティックタイプのこと。』と記載されている(乙8)から、菓子類の名称の一部として用いられた場合、棒状の形状を有する菓子を意味するものと理解される。(省略)本願商標の指定商品は、第30類『あずきを加味してなる菓子』を指定商品とするものであるところ、菓子業界では、アイスキャンデー等の棒状の氷菓子のほか、棒状の形状を有するそれ以外の菓子に、『○○(原材料又は風味等)バー』と称するものが存在することが認められる。(省略)本願商標が指定商品について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者は、小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる。そして、本願商標は、『あずきバー』という標準文字からなるものであるにすぎないから、指定商品の品質、原材料又は形状を普通に用いられる方法で表示したものというほかない。」として商標法3条1項3号に該当すると判断しました。
争点2:商標法3条2項該当性に係る認定判断の誤りについて
知財高裁は、原告の販売実績及びに、宣伝広告実績、知名度等を考慮して3条2項に該当すると判断しました。
争点3:商標法4条1項16号該当性に係る認定判断の誤りについて
知財高裁は「本願商標は、前記1に説示のとおり、指定商品について使用された場合、これに接した菓子の取引者、需要者が小豆又はそれから作られたあんを含有する棒状の菓子を想起し、本願商標が商品の品質、原材料又は形状を表しているものと認識すると認められる一方、本願商標には、それ以上に商品の品質について特段の観念を生じさせる部分が存在しない。そうだとすると、本願商標は、商品の品質の誤認を生じるおそれがある商標ということはできない。」として商標法4条1項16号に該当しないと判断しました。
被告である特許庁が、本願商標が「あずきを原材料とするアイス菓子」を認識させるから、それ以外の商品に使用するときにはその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると主張している点については、知財高裁は、「ある商標が品質について誤認を生じさせるおそれがあるか否かは、当該商標の構成自体によって判断すべきところ、本願商標は、それ自体から『あずきを原材料とするアイス菓子』を直ちに認識させるものではないから、被告の上記主張は、失当である。」として特許庁の主張を退けました。