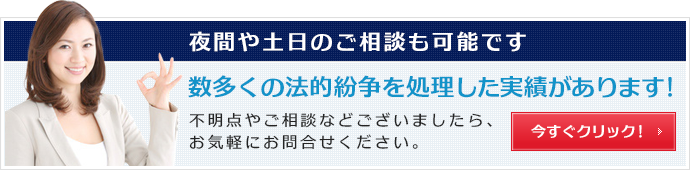原告は、被告の商標「NINA L'ELIXIR」(以下、「本件商標」とする。)は原告所有の引用商標1~3に類似するなどとして商標法4条1項11号、15号で無効審判を請求しましたが、特許庁は、本件商標は、「NINA L'ELIXIR」の構成全体がまとまりよく一体的に表されており、構成全体として一種の造語と理解されるものであり、本件商標から「ELIXIR」の部分のみを抽出して認識するとはいえない等として、請求不成立の審決をしました。原告はこれを不服として本件訴訟を提起しました。
財高裁は、「本件商標についてみると、外観上、本件商標を構成する各文字の大きさ及び書体は同一の全角で、等間隔でまとまりよく一体的に表されており、『NINA』と『L'ELIXIR』の間に空白部分があるものの、その広さは、半角程度にすぎず、全体として横に一行でまとまりよく表されているものであり、『L'ELIXIR』の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできず、まして、『ELIXIR』の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。...原告は、本件商標『NINA L'ELIXIR』を構成する12文字のうち、『ELIXIR』の文字列が占める割合は半分の6文字にも及ぶことから、『ELIXIR』の部分が『L'ELIXIR』の部分の一部にすぎないものとして捉えられるとは考え難く、また、『ELIXIR』の文字列の前部に『'』の記号が配されていることも考慮すると、簡易迅速を尊ぶ取引の場においては、視覚的に『L』との結合性が否定され、『ELIXIR』の部分のみが印象付けられやすいと主張する。しかし、『L'』は、フランス語の表記により、冠詞『Le』の母音字『e』省略して代わりに『'』(アポストロフ)を表示し、後ろに来る語と結びつけて1つの単語として称呼するもので、エリズィヨンと呼ばれるものであるから、フランス語の文法を認識している者であれば、『L'ELIXIR』から『L'』を分離して『ELIXIR』のみを1つの単語として認識するということはない。また、フランス語の文法について知識のない者であっても、本件商標の『L'ELIXIR』の文字部分を視覚的に捉えると、『L』と『'』、と『'』と『E』との間隔は、その後に続く『E』と『L』、『L』と『I』との間隔と同じであるから、『L'ELIXIR』を一体のものとして捉えるのが通常であると考えられる。 ...本件商標は、『L'Elixir』の文字部分あるいは『ELIXIR』の文字部分だけが独立して看取されることはないから、本件商標の『L'ELIXIR』の文字部分又は『ELIXIR』の文字部分が独立して、本件指定商品の取引者や需要者に対して、引用商標の商標権者である原告が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであったということはできず、他にこのようにいえるだけの事実は認められない。さらに、『NINA』の文字は、本件商標の指定商品に関連する一般的、普遍的な文字であるとはいえないから、『NINA』の文字部分に自他商品を識別する機能がないということはできない。このほかに、本件商標について、その構成中の『L'ELIXIR』の文字部分あるいは『ELIXIR』の文字部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないから、本件商標と引用商標の類否を判断するに当たっては、その構成部分全体を対比するのが相当であり、たとえ、引用商標が、本件指定商品の取引者や需要者の間で周知であったとしても、本件商標の『L'ELIXIR』の文字部分あるいは『ELIXIR』の文字部分だけを比較の対象として類否の判断をすることは許されないというべきである。」として4条1項11号に該当しないとの判断を示しました。
また、知財高裁は、「本件商標を見れば、『NINNA』の部分は、NINNA RICCI社の社名から採ったものであることが容易に理解でき、その『NINNA』の部分は、本件商標の構成全体の前半部分に配置されており、印象に残りやすいことから、本件商標を付した商品がNINNA RICCI社の商品であることは、本件指定商品の取引者や需要者が容易に理解、認識し得るものである。したがって、本件商標を本件指定商品に使用した場合、原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあると認めることはできず、他に、本件商標が他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるといえるだけの事実は認められない。」として4条1項15号にも該当しないとの判断を示しました。
NINA L'ELIXIR事件 知財高裁平成25年4月24日判決
Meiji事件 知財高裁平成26年2月5日判決
被告は、第30類「学校給食用の菓子及びパン」を指定商品とし、橙がかった赤色の三つの半円をドーム状に組み合わせた図形の下に、左から青色で二つのだ円形をハート型に重ねた形状(本件図形)と「eiji」の文字を配してなる登録第5081512号商標(本件商標。平成18年5月25日出願、平成19年10月5日設定登録)の商標権者を持っています。原告は、本件商標は原告の商標と類似するとして4条1項11号及び4条1項15号で無効審判を請求しましたが、請求不成立となりました。原告はこれを不服として本件訴訟を提起しました。
知財高裁は4条1項11号及び4条1項15号について、それぞれ以下のように判断しました。
4条1項11号について知財高裁は「本件商標と引用商標を比較すると、まず、本件商標は、上段において三つの半円をドーム状に模した図形を配しており、下段における本件図形が上記のとおり特定の文字と認識できない上に、右側のアルファベットと違って太さが均一であるという特徴があり、『eiji』部分と一体化した文字として見ることが困難であるという点において、やや装飾化された欧文字のみからなる引用商標1ないし3と明確な差異が存在するから、両商標は、外観において顕著な違いがあり、異なる印象を与える。したがって、両商標は、外観上紛れるおそれはない。次に、称呼の点において、本件商標は、上記のとおり本件図形が特定の文字と認識できないことからすれば、『エイジ』の称呼が生じることになる。これに対し、引用商標の称呼は『メイジ』であり、本件商標と音節の数が同一である上、第二音、第三音を共通にし、語頭音の母音部分も同じ『e』であるが、「メイジ」の語頭音の子音は「m」で両唇鼻音であって聞き取ることは容易であり、かつ、これが語頭に配されていることからしても、区別することは容易である。そして、三音しかない短い構成の称呼において、最初の一音が異なることによる称呼全体に与える影響は小さくない。したがって、両商標が紛れるおそれはない。さらに、上記称呼の違いから観念についても共通性はなく、両商標が紛れるおそれはない。」として本件商標と引用商標は類似しないと判断しました。
4条1項15号について知財高裁は、引用商標の周知性、及び本件商標と引用商標の指定商品の共通性については認めました。その上で、本件商標と引用商標に出所混同のおそれがあるかについては、知財高裁は「明治パン株式会社の取引先である学校関係者が本件商標に接した場合に、該会社名との関連性のためにこれを『メイジ』と呼称したとしても、そのような取引者は、明治パン株式会社の概要をある程度認識した上で取引関係に入るはずであって、その判断能力や前提知識からすると、原告とは別の会社であることはもちろんのこと、原告と何ら関係のない会社であると理解すると考えられるから、明治パン株式会社の商品を原告と経済的、組織的な何らかのつながりがある者の業務に係る商品と混同するおそれはないというべきである。これに対し、具体的に本件商標が指定商品に付されたという使用態様は現時点で証拠上明らかでないが、仮に指定商品における一般的取引者が本件商標を付した商品に接した場合には、前示のとおり、本件図形を『M』と判読できず、何らかの文字と関連づけることができない以上、本件商標からは『エイジ』の称呼しか生じない。そして、本件商標の称呼は、原告の商号の称呼の要部である『メイジ』の前後に何らかの別の言葉が付加するわけでもない。原告の商号の呼称の要部は『メイジ』のみと認められるから、本件商標の称呼である『エイジ』は、複数の要部から構成される商号のうち、その一部だけが省略されて用いられたり、一部を共通にしたりするものでもない。アルファベットで表記された場合の最初の文字が欠ける結果、日本語としては最初の音が完全に異なることとなったものである。しかも、両商標は、発語時に三音節しかない中で最も重要な語頭部分の音が異なっており、共通の発音部分から原告や引用商標まで想起・連想することは困難である。したがって、本件商標が付された商品を原告と経済的、組織的な何らかのつながりがある者の業務に係る商品であると誤信するとは認められないから、混同のおそれはない。」との判断を示しました。
Yチェア事件 知財高裁平成23年6月29日判決
原告は、指定商品を第20類「家具」(拒絶査定不服審判請求後に指定商品を「肘掛椅子」に減縮補正)として肘掛椅子の立体形状について立体商標で商標登録出願を行いましたが、3条1項3号に該当するとして拒絶査定を受けた為、拒絶査定不服審判を請求しましたが、請求不成立となりました。原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本願商標の特徴的形状を備えた原告製品(肘掛椅子)は、参加人により1950年(昭和25年)に発売されて以来、材質や色彩にバリエーションはあるものの、その形状の特徴的部分において変更を加えることなく、継続的に販売されている。...。原告製品の販売地域は全国に及んでおり、資料等により、判明している限りでも、平成6年7月から平成22年6月までの間に、合計9万7548脚が販売されており、このような販売数量は、食卓椅子の販売数量全体と比較すれば必ずしも多いとはいえないものの、1種類の椅子としては際だって多いといえる(なお、原告製品は、既製品であり、注文を受けてから作る受注品ではない。)。原告製品は、1960年代以降、日本国内においても、雑誌等の記事で紹介され、日本で最も売れている輸入椅子の一つとの評価がされている。また、原告製品は、インテリア用語辞典、インテリアコーディネーター試験問題集等の家具業界関係者向けの書籍や、中学生向けの美術の教科書に掲載されるなどの実績を残している。さらに、原告により相当の費用を掛けて、多数の広告宣伝活動が行われている。原告は、原告製品について、国内有数の家具展示会等に出展したり、自社ショールーム、百貨店等における展示会を開催したりするなど、原告製品の周知性を高めるための活動を継続して行った。こうした継続的な広告宣伝活動等により、原告製品は、一部の家具愛好家に止まらず、広く一般需要者にも知られるものとなっているということができる。...【1】原告製品は、背もたれ上部の笠木と肘掛け部が一体となった、ほぼ半円形に形成された一本の曲げ木が用いられていること、座面が細い紐類で編み込まれていること、上記笠木兼肘掛け部を、後部で支える『背板』(背もたれ部)は、『Y』字様又は『V』字様の形状からなること、後脚は、座部より更に上方に延伸して、『S』字を長く伸ばしたような形状からなること等、特徴的な形状を有していること、【2】1950年(日本国内では昭和37年)に販売が開始されて以来、ほぼ同一の形状を維持しており、長期間にわたって、雑誌等の記事で紹介され、広告宣伝等が行われ、多数の商品が販売されたこと、【3】その結果、需要者において、本願商標ないし原告製品の形状の特徴の故に、何人の業務に係る商品であるかを、認識、理解することができる状態となったものと認めるのが相当である。」として3条2項該当性を認め、審決を取消しました。
CHOOP事件 知財高裁平成23年6月29日判決
原告は、「CHOOP」(以下、「本件商標」とする。)の商標権者です。原告の商標は、引用商標「Shoop」と同一の称呼「シュープ」を生じるものであり、その外観上の相違、観念において両者が比較できないことを考慮しても、類似の商標といえるとして本件商標を4条1項11号該当性を理由として無効としました。原告はこれを不服として本件訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本件商標と引用商標は、『シュープ』の称呼を生じ得る点で称呼において類似するものの、外観において相違する。また、特定の観念は生じないと解されるから、観念において類否を判断することはできない。また、本件商標に係る取引の実情をみると、原告は、前記1の(4)のとおり、商標『CHOOP』について、長期にわたり、指定商品等への使用を継続してきたこと、雑誌、新聞、テレビや飛行機内での番組提供、テレビCM等を利用して、宣伝広告活動を実施してきたこと、ファションブランド誌や業界誌にも紹介されていること、『ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブランド』を想起させるものとして、需要者層を開拓してきたこと、その結果、同商標は、ティーン世代の需要者に対して周知となっていることが認められる。他方、引用商標を構成する『Shoop』の欧文字は、『セクシーなB系ファッションブランド』を想起させるものとして、需要者層を開拓してきた、そして、商標『CHOOP』の使用された商品に関心を示す、『ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション』を好む需要者層と、引用商標の使用された商品に関心を示す、いわゆる『セクシーなB系ファッション』を好む需要者層とは、被服の趣向(好み、テイスト)や動機(着用目的、着用場所等)において相違することが認められる。そうすると、本件商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、取引の実情等において、原告による『CHOOP』商標が広く周知されていること、需要者層の被服の趣向(好み、テイスト)や動機(着用目的、着用場所等)が相違することに照らすならば、本件商標が指定商品に使用された場合に取引者、需要者に与える印象、記憶、連想は、引用商標のそれとは大きく異なるものと認められ、称呼を共通にすることによる商品の出所の誤認混同を生じるおそれはないというべきである。」として審決を取消しました。
ASCEND事件 知財高裁平成25年6月26日判決
原告は、欧文字「ASCEND」からなり、第10類「医療用機械器具、バルーン拡張カテーテル」を指定商品とする商標登録出願(以下「本願」という。また、本願に係る商標を「本願商標」という。)の出願人です。本願商標は、「ASCENT」を引用商標として4条1項11号に該当するとして拒絶査定となったので、原告は拒絶査定不服審判を請求しましたが、請求不成立審決を受けました。原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本願商標は、『ASCEND』の欧文字6からなり、『登る、上る、上昇する』等の意味を有する英語の動詞である。本願商標から、『アセンド』の称呼、及び『登る、上る、上昇する』との観念が生じる。他方、引用商標は、『ASCENT』の欧文字6字からなり、『ASCEND』の派生語であり、『登ること、上昇』等の意味を有する英語の名詞である。引用商標から、『アセント』の称呼、及び『登ること、上昇』との観念が生じる。本願商標『ASCEND』と引用商標『ASCENT』は、『ASCEN』の綴りを共通にし、語尾の『D』と『T』の文字において相違するにすぎないから、外観において類似する。本願商標からは、『登る、上る、上昇する』との観念が生じ、引用商標からは、『登ること、上昇』との観念が生じ、観念において類似する。本願商標からは『アセンド』の称呼が生じ、引用商標からは『アセント』の称呼が生じ、両者は、いずれも4音であり、語頭からの3音『アセン』において共通し、語尾の『ド』と『ト』の音において相違するにすぎないから、称呼において類似する。また、本願商標について、取引者、需要者において、引用商標との間で、その出所を区別することができると解されるような格別の取引の実情が存在したと認めるに足りる証拠はない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、同一又は類似の商品に使用された場合には、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるといえる。本願商標の指定商品『医療用機械器具、バルーン拡張カテーテル』と引用商標の指定商品『医療用及び外科用機械器具』とは、いずれも『医療用機械器具』の範疇に属する商品であるから、同一又は類似の商品である。以上によれば、本願商標は、商標法4条1項11号に該当する。」として、原告の請求を棄却しました。
マッサージクッション事件 知財高裁平成25年5月29日判決
原告は、片仮名の「マッサージクッション」を標準文字で表記した商標(以下「本願商標」という。)について、指定商品を第10類「家庭用電気マッサージ器」として、商標登録出願(以下「本願」という。)をし、その後、指定商品を「クッション形状の家庭用電気マッサージ器」に補正しました。原告は3条1項3号に該当するとして拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求しましたが、特許庁は請求不成立の審決をしました。原告は、審決には3条2項該当性の判断について誤りがあるとして本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「認定事実によれば、『マッサージクッション』の文字からなる本願商標について、『使用された結果、需要者において、原告の業務に係る商品であると認識することができるもの』と判断することはできない。その理由は、以下のとおりである。すなわち、(1) 一般の家庭用電気マッサージ器等の製造、販売に係る取引者、需要者において、『マッサージクッション』の語は、『手軽に持ち運べて、クッションとしても使えるマッサージクッション。』等の用例にみられるように、『クッション形状のマッサージ器』を意味する普通名詞として用いられている。また、各製造者等において自社製品を宣伝広告する場合、及びネット販売業者において各社の商品を紹介する際に、当該商品の出所を示す必要がある場合には、『マカロンマッサージクッション・MC-301』、『オムロン クッションマッサージャHM-341-BW ブラウン』、『クロシオ マッサージクッション シフォン チョコレート CH-301-CH』など、商標等の出所表示を付加して使用することが通例である。(2) 本件商品に関する原告の宣伝広告及びテレビ、雑誌、新聞等における商品紹介をみると、『ルルド マッサージクッション』と表示される例が多い。また、原告は、『ルルド』シリーズで本件商品を含む各種家庭用マッサージ器のほか、バランスツール、ベッド等を販売しているが、本件商品の包装箱、取扱説明書、カタログや原告のウェブサイトには、四角で囲まれた図形及び欧文字『Lourde』の組合せからなり登録商標を示す『○R 』を併記した『ルルド標章』も表示されている。 (3) 以上の事実経緯に照らすならば、本件商品の包装箱、取扱説明書、カタログや原告のウェブサイトにおける本件商品の表示に接した需要者は、『ルルド』ないし『ルルド マッサージクッション』等により、本件商品の出所が原告であると認識しているのであって、『マッサージクッション』のみによって、出所が原告であると認識することはないと解するのが合理的である。なお、本件商品の包装箱やカタログには、『Massage』及び『CUSHION(Cushion)』と表示されているが、包装箱やカタログにはルルド標章も付されていることや、包装箱とカタログ以外では、欧文字の表示はほとんど使用されていないことからすると、このことから、『マッサージクッション』の表示のみで本件商品の出所を認識することができるということはできない。原告は、本件商品の販売数及び小型マッサージ機器のマーケットシェアが50パーセントを超えること等の点を主張する。しかし、そのような事実から、『マッサージクッション』の語が、使用された結果、需要者において、原告の業務に係る商品であると認識することができるものと解することは到底できず、この点の原告の主張は採用の限りでない。」として3条2項該当性を否定しました。
新型ビタミンC事件 知財高裁平成26年10月22日判決
原告は指定商品を第5類「サプリメント」とする標準文字商標「新型ビタミンC」(以下、「本願商標」とする。)について商標登録出願を行いましたが、3条1項6号に該当するとして拒絶査定(以下、「本件査定」とする。)を受けました。原告は拒絶査定不服審判を請求しましたが、今度は3条1項3号に該当するとして審判請求は不成立となりました。
原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「本願商標は、『新型ビタミンC』の文字を標準文字で横書きに表してなるものであり、『新型』の文字と『ビタミンC』の文字とを組み合わせた構成からなることは明らかである。そして、『新型』(従来のものとはかわって、新しく考案された型や形式。)も『ビタミンC』(人体に不可欠な微量栄養素であるビタミンの一種でCと名付けられており、水溶性で、新鮮な野菜・果実・緑茶などに多く含まれるもの。)も一般に広く知られている平易な語であり、『新型ビタミンC』の文字は、『従来のものとはかわって、新しく考案された型のビタミンC』程度の意味合いを表す複合語として容易に認識されるものである。そうすると、本願商標を、その指定商品である『サプリメント』に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、『従来のものとは違う新しく考案されたビタミンCを主成分としたサプリメント』であると理解し、当該商品の品質を表したものとして認識するといえる。したがって、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるもの(本願商標は標準文字で構成される。)であるから、商標法3条1項3号に該当する。...原告の主張は、本件査定において拒絶理由として挙げた商標法3条1項6号とは異なって、審決において同項3号に該当すると判断するのであれば、同号に基づく拒絶理由通知をする必要があるので、それをしなかった審決には、商標法55条の2第1項で準用する同法15条の2に違反する瑕疵があるとの趣旨と解される。(なお、商標法3条1項6号に該当する場合と同項1~5号に該当する場合とで、その適用に択一的な排斥関係はないから、同項6号に該当すると判断することが、同項3号には該当しないとの判断を前提とするものでなく、この点に係る原告の主張は、失当である。)。本件査定と審決は、いずれも、本願商標から『新タイプのビタミンC』との認識が生じることを前提として、これを指定商品に使用しても出所表示機能を有するものではなく、商標法3条1項所定の商標登録の要件を欠く商標に該当するという共通の結論を示したものといえる。両者は、その判断の内容において実質的に相違するものではなく、その審理対象も、『新タイプのビタミンC』の意義という同一のものであって(そして、原告は、実際に、本件における主張と同旨の意見書を提出している。)、審決が、実質的に新たな拒絶理由を示したものということはできない。したがって、審決に、『拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。』とする商標法55条の2第1項で準用する同法15条の2に違反するところはなく、原告の上記主張は、採用することができない。」として原告の請求を棄却しました。
ALL STATE事件 平成25年5月30日判決
原告は本件商標「ALL STATE」、指定商品「被服」について商標法50条1項に基づき不使用取消審判を請求しました。特許庁は、「本件商標の通常使用権者である株式会社レイラニトレーディング(以下『レイラニ社』という。)が平成24年2月6日に、本件商標と社会通念上同一の商標を使用して革製ジャケット(以下『本件商品」という。)の広告をインターネットを介して行ったものと認めることができ、これは『商品に関する広告情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為』(商標法2条3項8号)に該当する。」として、請求不成立審決をしています。
知財高裁は、「使用標章は上記1(1)【本件標章】のとおりであるところ、本件商標における文字に『ALL』と『STATE』の間に空白がないが、その文字は文字枠およびアメリカ合衆国の地図をあしらった図形部分を凌駕して独立の標章と認識し得るものであり、社会通念上本件商標と同一の商標と認められる。また、使用商品は『革製ジャケット』であり、本件商標の指定商品である『被服』の範ちゅうの商品と認められる。商標使用は、商標権者が登録商標管理として入念に配慮しなければならず、その関係の内部資料を保管しているべきであって、たやすく立証可能な事実であるのに、被告はネットの掲載などの断片的な証拠を提出するのに甘んじている。しかし、上記1認定の各事実を総合すると、レイラニ社は『2012-02-06』すなわち平成24年2月6日に『ALL STATE』の文字を含む本件標章を取り入れた革製ジャケットについてネット上で広告・宣伝したことはかろうじて認めることができる。同社のこの行為自体は、商標法2条3項8号に規定する『商品に関する広告・・・を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為』に該当するというべきである。なお、アメーバブログの登録者である会員が個人であってもリンク元は当該個人の所属する会社のショップサイトであるから、リンク元のショップで販売している商品の広告・宣伝をしていることに何ら変わりはない。」として商標法2条3項8号の使用のあったことを認めた審決に誤りはないとして、原告の訴えを棄却しました。
御用邸事件 知財高裁平成25年5月30日判決
原告は、指定商品を第30類「菓子及びパン」とする商標「御用邸」(以下「本件商標」とする。)の商標権者でした。しかし、被告に無効審判を請求され、本件商標は4条1項7号に違反して登録されたものであるとして商標を無効にされてしまいました。原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
知財高裁は、「『御用邸』とは皇室の別邸を意味し、天皇又は皇族の静養等に用いられるもので、現在、那須御用邸、葉山御用邸、須崎御用邸の3つがあること、御用邸は国有財産であって、行政財産のうち皇室用財産に属し、宮内庁が管理するものであることが認められる。『御用邸』が皇室の別邸であることは広く知られており、『御用邸』の文字には、皇室と関係があるかのように感じさせる効果があり、顧客誘因力がある。そうすると、皇室と何らの関係もない者が、自己の業務のために指定商品について『御用邸』の文字を独占使用することは、皇室の尊厳を損ね、国民一般の不快感や反発を招くものであり、相当ではない。このことは、本件商標の登録査定時である平成7年11月16日においても、現在でも同様である。したがって、本件商標は、その登録査定時において既に、指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであったと認めることかできる。そうすると、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であり、その登録は、7号に違反してされたものであるから、商標法46条1項1号により登録を無効とした審決に誤りはない。」として原告の請求を棄却しました。
ブルーノート事件 知財高裁平成23年9月14日判決
原告は、「BLUE NOTE」又は「ブルーノート」という商標(以下、これらをまとめて「引用商標」とします。)を引用して、本件商標の登録は、商標法4条1項15号、19号に該当するなどと主張し、本件商標登録を無効とすることを求めて、審判請求をしましたが、特許庁は、本件審判の請求は成り立たないとする旨の審決をしました。原告はこれを不服として本件審決取消訴訟を提起しました。
本件は、知財高裁が「総合小売等役務」及び「特定小売等役務」の独占権の範囲について言及した点で注目を集めた事件です。
知財高裁は、「まず、『特定小売等役務』においては、取扱商品の種類が特定されていることから、特定された商品の小売等の業務において行われる便益提供たる役務は、その特定された取扱商品の小売等という業務目的(販売促進目的、効率化目的など)によって、特定(明確化)がされているといえる。そうすると、本件においても、本件商標権者が本件特定小売等役務について有する専有権の範囲は、小売等の業務において行われる全ての役務のうち、合理的な取引通念に照らし、特定された取扱商品に係る小売等の業務との間で、目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定されると解するのが相当である(侵害行為については類似の役務態様を含む。)。 次に、『総合小売等役務』においては、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品』などとされており、取扱商品の種類からは、何ら特定がされていないが、他方、『各種商品を一括して取り扱う小売』との特定がされていることから、一括的に扱われなければならないという『小売等の類型、態様』からの制約が付されている。したがって、商標権者が総合小売等役務について有する専有権の範囲は、小売等の業務において行われる全ての役務のうち、合理的な取引通念に照らし、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品』を『一括して取り扱う』小売等の業務との間で、目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定されると解するのが相当であり(侵害行為については類似の役務態様を含む。)、本件においても、本件商標権者が本件総合小売等役務について有する専有権ないし独占権の範囲は上記のように解すべきである。そうだとすると、第三者において、本件商標と同一又は類似のものを使用していた事実があったとしても、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品』を『一括して取り扱う』小売等の業務の手段としての役務態様(類似を含む。)において使用していない場合、すなわち、【1】第三者が、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る』各種商品のうちの一部の商品しか、小売等の取扱いの対象にしていない場合(総合小売等の業務態様でない場合)、あるいは、【2】第三者が、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る』各種商品に属する商品を取扱いの対象とする業態を行っている場合であったとして、それが、『衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う』小売等の一部のみに向けた(例えば、一部の販売促進等に向けた)役務についてであって、各種商品の全体に向けた役務ではない場合には、本件総合小売等役務に係る独占権の範囲に含まれず、商標権者は、独占権を行使することはできないものというべきである(なお、商標登録の取消しの審判における、商標権者等による総合小売等役務商標の『使用』の意義も同様に理解すべきである。)。『総合小売等役務商標』の独占権の範囲を、このように解することによって、はじめて、他の『特定小売等役務商標』の独占権の範囲との重複を避けることができる。」との判断を示しました。
上記の判断基準に立ったうえで、4条1項15号該当性について以下のように判断しています。
4条1項15号該当性について知財高裁は、「原告は、米国カリフォルニア州ハリウッドに本社を置く大手のレコード製作、販売会社の一つであり、米国ニューヨークで、昭和14年に創設されたジャズ音楽専門のレコード製作、販売会社『BLUE NOTE(ブルーノート)』(以下『ブルーノート社』という。)の親会社である。ブルーノート社は、ジャズ専門レーベルとして、今日に至るまで数多くのジャズ演奏家等の演奏曲を収録したレコード(CDも含む。)に『BLUE NOTE(ブルーノート)』の標章を付して、販売をした。また、我が国において、ブルーノート社は、遅くとも昭和40年代には、レコード(CDも含む。)の販売を開始し、また、昭和61年から平成8年まで、数々の著名ミュージシャンが出演した『ワン・ナイト・ウィズ・ブルーノート』のコンサート等を開催した。これらの事実によれば、本件商標の登録出願前から、『BLUE NOTE(ブルーノート)』の標章(引用商標)は、これに接する音楽関連の取引者、音楽愛好家などの需要者において、原告ないし原告の子会社であるブルーノート社の製作、販売等に係る『レコード(CDも含む。)』であると広く認識、理解されていたと認められる。しかし、同標章によって、原告ないし原告の子会社等の出所を示すものとして広く認識されるのは、商品『レコード(CDも含む。)』の販売等、又は、せいぜい同商品の販売等をする過程で行われる便益の提供に関連するものに限られるのであって、上記範囲を超えて広く知られていたとまでは認めることができない。...原告の引用商標の使用態様は、商品『レコード(CDを含む。)』の販売等又は同商品を販売等する過程で行われる便益の提供に限られるものであり、本件総合小売等役務を指定役務とする本件商標権を被告が有することによって保護される独占権の範囲に含まれるものではないから、被告が同商標を使用したとしても、需要者、取引者において、その役務の出所が原告であると混同するおそれがあると解することはできない。また、本件特定小売等役務には、『レコード(CDも含む。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』は、含んでいないから、本件商標を本件特定小売等役務に使用することによって、原告の業務に係る商品又は役務との間で、出所の混同を来すことはない。」として4条1項15号に該当しないとした審決に誤りはないとしました。